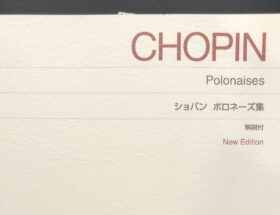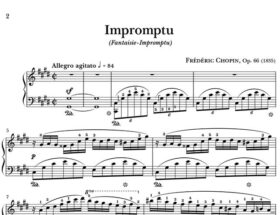皆様、こんにちは。
今回はドビュッシーという作曲家をご紹介していきます。
Claude Debussy

クロード・ドビュッシー(1862〜1918)は、これまでのクラシック音楽の伝統を外れ、新たな道を切り開いたフランスの作曲家です。
ドビュッシーは自身の幼少期のことをあまり語ろうとしなかったので、詳しくは記録されていませんが8歳ごろから知り合いの手ほどきで、ピアノや音楽基礎を学んでいたようです。
やはり才能があったようで、10歳ではパリ音楽院に入学しました。
もともとはピアニストを目指してピアノ科にいましたが、思うように成績が残せず17歳でピアノ伴奏法のクラスに移ることを決めました。
またこの頃から作曲に手を伸ばし始めており、初期はチャイコフスキーやワーグナーの影響を受けていたようです。
1883年、1884年(審査員にはサン=サーンス)に挑戦したローマ賞では続けて2位、1位を受賞し作曲家としての頭角を表してきました。
1889年はドビュッシーにとって転機の年となります。
この歳に行われたパリ万国博覧会でジャワ音楽(ガムラン)を聞いた彼は衝撃を受け、今後の自身の作品だけでなく「クラシック音楽」の流れすら変えることとなります。
1905年にはエンマ・バルダックと結婚し、娘が誕生します。
1910年には「前奏曲集 第1巻」を発表し、ピアノ曲において作曲家のキャリアを確立しました。
1914年、第1次世界大戦の勃発とともに、自身の病気も見つかります。
その後も「12の練習曲」「ヴァイオリンソナタ」「チェロソナタ」などの大作を残しますが、未完成の曲を残して、1918年直腸がんで亡くなります。
ここで有名曲をご紹介いたします。
「月の光」
「交響詩 海」
「牧神の午後への前奏曲」
ドビュッシーとピアノの関係性
ドビュッシーはピアノ曲において成功を多く残した作曲家だと言えるでしょう。
「2つのアラベスク」「版画」「喜びの島」「子供の領分」などの有名曲がいくつもありますが、一番はやはり「前奏曲集」でしょうか。
「前奏曲集」は全2巻で、全24曲となっています。
面白いのが、24曲それぞれに曲名は無く、その代わりに曲の最後に「・・・」が付け加えられたタイトルがドビュッシーのイメージとして書かれています。
第1巻は約2ヶ月で書かれており、ショパンに学び、ムソルグスキーや東洋音楽の影響を受け、クラヴサン(チェンバロ)音楽に基礎を置く、ドビュッシーの作曲法が全面に出ている曲集です。
第2巻は第1巻の2年後の作曲されており、実験的で抽象的な作品が多いです。
この第2巻は、20世紀音楽の先駆けとして評価されています。
第1巻
第2巻
最後に
いかがでしたでしょうか。
個人的にドビュッシーには思い入れがあります。というのも、ドビュッシーの「第一狂詩曲」というクラリネットのための作品があるのですが、コンクールのために長期間さらっていて、大学1年のときは半分をこの曲と過ごしたと言っても過言ではないのです。
さて、今回大きく取り上げた「前奏曲集」ですが、第1巻に入っている「亜麻色の髪の乙女」が、otto
piano concours vol.2 supported by Technics の中級課題曲になっております。
詳しくはコチラ!!
もちろん楽譜もottoで取り扱っておりますので、是非是非お店に足をお運びくださいませ。